はじめに
このドキュメントは遊戯王マスターデュエル初心者向けのものです。ランクマッチでダイヤモンド帯・マスター帯あたりを狙う人向けに書かれています。 遊戯王のルールは非常に複雑ですべてを把握するのは難しいです。そのため、このドキュメントでは正確性はやや犠牲にしてとりあえず初めてみることに特化して必要最低限の知識を身につけることを目的としています。
また、このドキュメントはデッキの個別の回し方は解説しません。こちらは最新の情報を発信している他の方のブログや動画を見た方がいいでしょう。
このあたりの知識・理論は実際にランクマッチをやっていくうちに自然と学べるものではありますが、このようにまとまって文章化したものを読んだ方が始めやすいという方もいるのではと思い書いています。
ルール
遊戯王のルールは非常に複雑です。とりあえずチュートリアルをやれば大まかには理解できると思いますが、細かい部分は把握が難しいと思います。 このドキュメントでは基本的なルールの解説はせず、わかりずらい箇所や実践でよく使う箇所に絞って何点か解説します。 わかりやすさを優先しているため、細かい例外などは省略していることがあります。
基本的なルールについて学びたい人はチュートリアルをとりあえずこなすか、公式のあそびかたのページを読むといいでしょう。
チェーンと優先権
「チェーン」とは魔法・罠・モンスター効果の発動に対して、別のカードの効果の発動を重ねて宣言する行為やそのシステムのことを指します。 遊戯王の最も特徴的なシステムがチェーンです。このシステムにより、カード効果の応酬が可能になり、遊戯王ならではの駆け引きが生まれます。
「優先権」とはカードを最初に発動する権利です。この優先権を持っているプレイヤーでないとカードの発動を宣言できません。 こちらもチェーンと深く関わるシステムなので、一緒に説明します。
チェーンの流れ
自分や相手がカードを発動すると、その発動に対して速攻魔法や罠カードや一部のモンスター効果を発動させチェーンを組むことができます。 チェーンは、最後に発動したカード効果から順に解決されます。 例をあげて説明します。
- ターンプレイヤーが《増援》を発動する(チェーン1)
- 相手プレイヤーが《灰流うらら》を発動する(チェーン2)
- ターンプレイヤーが《墓穴の指名者》を発動する(チェーン3)
- 相手プレイヤーが《神の宣告》を発動する(チェーン4)
この場合、チェーンは最後に発動したカードである《神の宣告》から順に解決されます。 解決の流れは以下のとおりです。
- 《神の宣告》の効果が解決する。《神の宣告》の効果により、《墓穴の指名者》の発動が無効になる。
- 《墓穴の指名者》の発動が無効になったため、何も起きない。
- 《灰流うらら》の効果が解決する。《灰流うらら》の効果により、《増援》の戦士族モンスターを手札に加える効果が無効になる。
- 《増援》の効果が無効になり、何も起きない。
今回は効果や発動を無効にするカードがあるため、チェーンが解決されるときに何も起きないことがありましたが、必ずしもカードを無効にする効果をチェーンする必要はないので、無効になっていなければ通常通り効果が発動されます。
チェーンができるカード
カードの効果には「スペルスピード」というのが設定されています。スペルスピードは1から3までの3段階があり、スペルスピードが2以上の効果はチェーンを組むことができます。 また、発動した効果のスペルスピード以上のスペルスピードを持っていないとチェーンを組むことができません。つまり、スペルスピード3の効果に対してはスペルスピード2の効果をチェーンできません。
スペルスピード1のカードは速攻魔法以外の魔法カードと一部の例外を除くモンスターの効果です。これらのカードは他のカードの発動に対してチェーンを組むことができません。
スペルスピード2のカードはカウンター罠以外の罠カード・速攻魔法・モンスター効果のうち誘発即時効果と呼ばれるものです。これらのカードはチェーンを組むことができます。 モンスターの誘発即時効果は使用タイミングが限定されているが、相手ターンにも発動できる特別な効果です。先程のチェーンの例であげた《灰流うらら》の効果はこのカテゴリーに属すため、チェーンを組むことができました。 発動タイミングが限定されていない場合でも、「この効果は相手ターンでも発動できる」といった表記がある場合、こちらも誘発即時効果として扱われます。 例としては《D-HERO デストロイフェニックスガイ》の②の効果などがあります。
②:自分・相手ターンに発動できる。自分フィールドのカード1枚とフィールドのカード1枚を破壊する。
このような誘発即時効果は自分のメインフェイズ以外にも好きなタイミングでスペルスピード2の効果として発動することができます。
スペルスピード3のカードはカウンター罠のみです。つまり、カウンター罠の効果に対してはカウンター罠でしかチェーンを組むことができません。
また、スペルスピード2以上の効果はクイックエフェクトとも呼ばれ、次で説明する優先権を持つプレイヤーであれば相手ターンでも発動することができます。
優先権
カードを最初に発動できるのは「優先権」を持っているプレイヤーです。優先権が移ることで、相手プレイヤーがカードを発動する権利を得ることができます。 最初に優先権を持っているのはターンプレイヤーです。ターンプレイヤーが優先権を使いカードを発動させること、もしくはターンをすすめる処理の過程で優先権を放棄することで相手プレイヤーに優先権が移ります。
具体的には以下のような場合に優先権が移ります。
- ターンプレイヤーが魔法カードを発動する
- カードの効果を発動すると、そのカードのチェーンしてクイックエフェクトを発動するために相手に優先権が移ります
- ターンプレイヤーがモンスターを召喚し、次の行動に移る前
- モンスターの召喚後の召喚時の効果がある場合、まずターンプレイヤーがその効果を発動できます
- 特に誘発効果がない場合、優先権が移り相手プレイヤーがクイックエフェクトを発動できるようになります
- ターンプレイヤーがメインフェイズの終了を宣言する
- フェーズの切り替え時やバトルフェイズの各ステップには優先権が移り、相手プレイヤーがクイックエフェクトを発動できるようになります
優先権のルールは細かく、厳密に説明しようとすると難しい部分でもあります。 マスターデュエルでは自動的にこの優先権は処理されているため、実践で遊んでいると自然と覚えることができるでしょう。 ゲーム設定の「発動確認」の設定を「発動確認する」にしておくと、優先権が移り発動可能なカードがあるタイミングすべてで確認を求められるようになります。 「オート」のままだと一部のタイミングで確認がスキップされること(フェーズの切替時など)があるので気をつけましょう。 最初のうちは煩わしいかもしれませんが、一度「発動確認する」にしておき、どのようなタイミングがあるかを勉強するのもよいでしょう。
効果・発動の無効
初心者のよくある間違えの一つが効果が無効になる処理についてです。 遊戯王において、魔法カードやモンスターカードの効果の発動に対して、その魔法カードやモンスターカードを破壊する効果を使っても効果は止まりません。
破壊と無効
具体的な例をあげながら説明します。
- 相手が《サンダー・ボルト》を発動する
- チェーンして自分が《サイクロン》を相手の《サンダー・ボルト》を対象に発動する
このような場合、以下のように効果が解決されます
- 《サイクロン》の効果が解決する。《サンダー・ボルト》が破壊される
- 《サンダー・ボルト》の効果が解決する。自分フィールドのモンスターがすべて破壊される
このように発動したカードを破壊したとしてもカードの効果は止まりません。 これは弾丸と銃の関係に例えられることがあります。弾丸が発動した効果で、魔法カードは銃です。銃を破壊してもすでに発射された弾丸は止めることができません。
無効
《サイクロン》は銃を破壊する効果でしたが、弾丸を止める効果を持つカードも存在します。こちらを使えば《サンダー・ボルト》の破壊効果を止めることができます。 例えば《神の宣告》や《ヴァレルロード・S・ドラゴン》の③の効果が該当します。
《神の宣告》の効果は以下のようになっています。
①:LPを半分払って以下の効果を発動できる。 ●魔法・罠カードが発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊する。 ●自分か相手がモンスターを召喚・反転召喚・特殊召喚する際に発動できる。それを無効にし、そのモンスターを破壊する。
《ヴァレルロード・S・ドラゴン》の③の効果は以下のようになっています。
③:相手の効果が発動した時、このカードのヴァレルカウンターを1つ取り除いて発動できる。その発動を無効にする。
それぞれ「発動を無効に」と書いてあります。このようなカードは効果を止めることができます。
「効果を無効に」と書いてあるカードでも効果を無効にすることができます。《琰魔竜 レッド・デーモン・アビス》の①の誘発即時効果がそれにあたります。
①:自分・相手ターンに、相手フィールドの表側表示カード1枚を対象として発動できる。そのカードの効果をターン終了時まで無効にする。 この効果を相手の《サンダー・ボルト》の効果にチェーンして《サンダー・ボルト》を対象にして発動することで、破壊効果を無効化することができます。
一応、発動を無効にするのと効果を無効にするのは厳密には違うのですが、両方とも効果を止めるものとして覚えておけば大概の場面で問題ないでしょう。
モンスター効果や罠カードの効果も同様に破壊するだけでは効果は止まらないので、上記のようなカードを使って効果や発動を無効にする必要があります。
永続系の場合
例外として永続魔法・装備魔法・フィールド魔法・永続罠カードように発動後もフィールドに残り続けるようなカードの効果は、そのカードを破壊することで効果を止めることができます。 これらのカードはフィールドに残っている状態でないと効果を適用できないというルールになっているからです。
永続系のカードは破壊以外にもフィールドから手札に戻すのような効果でもフィールドに残っていない状態になるので効果を止めることができます。 例えば《ファイアウォール・ドラゴン》の①の効果を使えば、永続系カードの効果を止めることができます。
①:このカードがフィールドに表側表示で存在する限り1度だけ、自分・相手ターンに、このカードの相互リンク先のモンスターの数まで、自分・相手の、フィールド・墓地のモンスターを対象として発動できる。そのモンスターを手札に戻す。
無効になったカードの扱い
実は効果が無効になったカードでも効果の発動は宣言できます。ただし、無効になっているので効果は不発になります。 例えば《無限泡影》の効果で効果が無効化された《ファイアウォール・ドラゴン》でも①の効果を発動させようとすることができます。リンク先のモンスターがフィルードから離れた場合、②の効果を発動するかどうかのダイアログも出てきます。いずれの場合も発動はされチェーンが組まれたりはしますが、効果は不発になり何も起こりません。
なお、無効になっているカードはカーソルを合わせると下のように表示が変わるので、こちらを確認しながらプレイするといいでしょう。
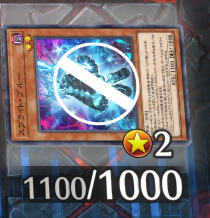
対象を取る
遊戯王の効果のテキストは独特で一見すると同じようなテキストでも違う意味を持つことがあります。 しかし、最近のカードは効果テキストの書き方が統一されているので、パターンを覚えておけば理解しやすいようになっています。 覚えておきたいパターンのひとつが「対象を取る」という表現です。
対象を取るとは
公式ルールブックには以下のように書かれています
対象を取る効果とは、効果を与える目標を選択して発動する効果の事を指します。 不特定のカードに効果を与えるものや、効果の処理時に目標が決定される効果は「対象を取る効果」ではありません。
具体的に見ていきましょう。《無限泡影》の①の効果は対象に取る効果です。
①:相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの効果をターン終了時まで無効にする。セットされていたこのカードを発動した場合、さらにこのターン中、このカードと同じ縦列の他の魔法・罠カードの効果は無効化される。
このカードを発動する場合、まず相手フィールドの表側表示モンスター1体を選択するようにダイアログが出てきます。そして相手の対象となるモンスターを選択した後、チェーンが組まれてチェーンの解決時にその選択したモンスターの効果が無効になるという流れになります。
対象に取らないカードの例としては《サンダー・ボルト》の効果があります。
①:相手フィールドのモンスターを全て破壊する。
実際に発動するとき特にダイアログが出てこない状態でチェーンが積まれるのがわかると思います。これはテキストからもなんとなく対象を取らない効果とわかるでしょう。
ややこしいのは、効果を適用するときにカードを選択するタイプのカードです。《D-HERO デストロイフェニックスガイ》の②の効果は対象を取る効果ではありません。
②:自分・相手ターンに発動できる。自分フィールドのカード1枚とフィールドのカード1枚を破壊する。
このようなカードの場合、チェーンを組む前ではなく実際にチェーンが解決されて効果が適用する場面でカードを選択することになります。
テキストの区別の仕方としては、「・・・を対象として発動できる」というような文が効果の最初に書いてあるかどうかで判定できます。そうではなく「発動できる」や「発動する」という文のあとに「選んで」などと書かれている場合は対象に取る効果ではないです。
対象に取る効果とそうでない効果の違い
対象に取る効果は発動を宣言すると同時に効果を与える目標を選ばなければなりません。一方で対象を取らない効果の場合は実際にチェーンが解決されて効果が適用するタイミングでカードを選ぶことになります。
例えば、《無限泡影》の発動にチェーンして《強制脱出装置》を無限泡影の対象となったモンスターを手札に戻すことで、無限泡影の効果は適用できなくなる、というようなことができます。 一方で《D-HERO デストロイフェニックスガイ》の②の効果に対して強制脱出装置を発動させても、効果を与える目標は効果解決時に選ぶことになるので、破壊されるカードを予め手札に戻しておくということはできません。
また、対象に取る効果に対して耐性を持つカードも存在します。相手の《真炎竜アルビオン》は①に書いてあるように効果の対象にとることができないため、《無限泡影》の対象として選ぶことができません。
①:相手はフィールドのこのカードを効果の対象にできない。
一方でこのようなカードは対象を取らない《D-HERO デストロイフェニックスガイ》のようなカードで破壊するモンスターとして選ぶことはできます。
コスト
カードの中には効果を発動するために何かしらのコストを支払う必要があるものがあります。 コストを支払う処理は効果による処理とはことなるため、いくつか気をつけるべき点があります。
似たようなものとして、アドバンス召喚やリンク召喚のような特殊召喚のためにコストを支払うものもあります。こちらも似た性質があるので合わせて説明します。
発動のためのコストの支払い
発動のためのコストを要求するカードの例として《サイバネット・マイニング》があげられれます。
①:手札を1枚墓地へ送って発動できる。デッキからレベル4以下のサイバース族モンスター1体を手札に加える。
「手札を1枚墓地へ送って」がコストです。このカードを発動するためにはまず手札を1枚墓地に送った後チェーンがつくられることになります。つまり、実際にチェーンが解決され効果処理が行われるタイミングではなく、発動を宣言するタイミングで手札を1枚墓地に送らなければなりません。 このカードに対して《灰流うらら》のようなカードで効果を無効にしても、コストを支払う部分は無効になりません。
コストを支払う処理は効果ではないので基本的には止めることはできません。 例として《おろかな埋葬》のデッキからカードを墓地に送る効果は《灰流うらら》で無効にすることができます。
①:デッキからモンスター1体を墓地へ送る。
一方で《彼岸の黒天使 ケルビーニ》の③の効果を見てみましょう。
③:デッキからレベル3モンスター1体を墓地へ送り、フィールドの「彼岸」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力・守備力はターン終了時まで、墓地へ送ったモンスターのそれぞれの数値分アップする。
同じく「デッキからレベル3モンスター1体を墓地へ送り」とあるので同じくデッキからカードを墓地に送る効果を無効にする《灰流うらら》で無効にできるように見えますが、このモンスターを墓地に送るテキストは「…として発動できる」という文の前に書かれているのでコストため、《灰流うらら》をそもそも発動する条件を満たさないです。
アドバンス召喚・特殊召喚のためのコスト
アドバンス召喚にはモンスターのリリースが必要です。リンク召喚などの特殊召喚にも素材を墓地に送る必要があります。これらのリリースや素材を墓地に送ることは、効果の発動のためのコストと同様に召喚・特殊召喚を無効にされても無効になりません。 例えば《神の宣告》でもリリースや素材を墓地に送る処理は止めることができません。
これの性質は《怪粉壊獣ガダーラ》のような相手のモンスターをリリースするモンスターでいきています。 このようなモンスターの特殊召喚そのものは無効にできますがリリースを止めることはできないので、確実に相手モンスターをリリースによって除去できます。
一方で《融合》による融合召喚の場合、融合素材を墓地に送る処理は効果の一部として扱われるのでこちらは素材を墓地に送る処理も無効にすることができます。
マスターデュエルでの戦略
とりあえずチュートリアルをだいたいやってルールをある程度把握した人向けの内容です。 現代のマスターデュエルでの一般的な戦略について具体例を交えながら解説していきます。 あくまで一般論の話なので、いくつかの例を出しますが現在の環境の最適解ではないことは留意してください。
先攻制圧
現代の遊戯王でもっともメジャーな戦術は、先攻プレイヤーが強力な妨害効果をもつカードを用意することで、後攻プレイヤーの行動を封じ、返しのターンで勝利を狙うというものです。 先攻で妨害効果を持つカードを並べることを「先攻制圧」といいます。
マスターデュエルでは先攻をとったほうが基本的には勝率が高いです。2024年に行われた世界大会では先攻をとったプレイヤーの勝率が6割近くあったようです。 そのため、まず先攻をとった場合にちゃんと勝つというのは非常に重要になっています。
先攻で出すべきカード
先攻で出すべきカードは後攻プレイヤーの動きを封じることができるカードです。単に強力なステータスや効果を持っているカードでは意味がない場合があります。 例えば《青眼の究極竜》のような攻撃力の高いモンスターを出せたとしても、現代環境では効果による除去は容易です。 《RR-アルティメット・ファルコン》のような効果耐性を持つモンスターも悪くないですが、攻撃力を上回られたり《閉ザサレシ世界ノ冥神》のリンク素材にするなどしてコストとして除去される抜け道があるといったように、攻略されるケースが結構あります。
相手の動きを封じるには、相手のカードをこちらの好きなタイミングで除去できたり、相手の効果を無効化するカードが有効です。 例えば《フルール・ド・バロネス》の②の効果は魔法・罠・モンスターの効果の発動を無効にし破壊する効果は非常に強力な妨害効果です。あらゆるカードの効果の発動を無効にできた上に破壊までするので、召喚されたモンスターカードの効果に対して発動すればフィールドに残らないのでその後にリンク素材にするといったこともできません。 《強制脱出装置》のように効果を無効にはしないが、単にモンスターを除去できるカードも妨害としては有効です。 EXデッキから召喚されたモンスターを除去できれば相手は再度そのモンスターを出すための条件を整えなければなりません。あるいはEXデッキから特殊召喚するための条件を整えないためにその素材となるモンスターを除去するのもよいでしょう。 除去はできなくても《無限泡影》のように効果を無効化するだけのカードも重宝されます。 現代遊戯王ではモンスターを次々に特殊召喚して、そのモンスターの強力な効果を利用してさらに展開・除去を行うという流れが多いので、その流れを食い止めることができます。
除去・無効化ができるカードといってもその発動できるタイミングも重要であることには注意しましょう。 《聖なるバリア -ミラーフォース-》は相手の攻撃表示のモンスターをすべて破壊するという強力な効果を持っています。 しかし、このカードを発動できるのは相手モンスターの攻撃宣言時のみです。メインフェイズの相手の展開を止めることはできません。現代環境ではメインフェイズの展開で罠カードを除去したり罠を無効にするカードを用意することはたやすいので、相手の妨害として機能させるには意外と難しいです。 むしろ《強制脱出装置》のように1体しか除去できないものの、自分で自由にタイミングを選んで除去できるというカードのほうが妨害としては使いやすいでしょう
【相剣】デッキでの展開例
ランクマッチで活躍するデッキの多くは先攻1ターン目で安定して妨害する手段を用意してきます。例として【相剣】デッキでの展開例を見てみましょう。
- 《相剣師-莫邪》を召喚する
- 召喚した莫邪の①の効果を発動し、手札の「相剣」カードか幻竜族モンスターを相手に見せて、星4のチューナーとなるトークンを特殊召喚する
- 莫邪とトークンの2体を素材として、星8の《相剣大師-赤霄》をシンクロ召喚する
- シンクロ素材となった莫邪の②の効果とシンクロ召喚に成功した赤霄の①の効果がそれぞれ発動する。莫邪の効果で1枚ドローして、赤霄の効果で「相剣」カードである《相剣軍師-龍淵》を手札に加える
- 手札の龍淵の①の効果を使用する。手札の「相剣」カードか幻竜族モンスターを捨てることで龍淵自信と星4のチューナーとなるトークンを特殊召喚する
- 龍淵とトークンを素材として、星10の《フルール・ド・バロネス》をシンクロ召喚する。この時、素材となった龍淵の②の効果により、相手に1200の効果ダメージを与える
このように、《相剣師-莫邪》というカード1枚と「相剣」カードか幻竜族モンスターの合計2枚のカードから2体の上級シンクロモンスターを並べることができました。 《相剣大師-赤霄》の②の効果により、相手ターンに自分の手札か墓地から「相剣」カードか幻竜族モンスターを除外することで、フィールドの効果モンスターの効果を無効化することができます。 《フルール・ド・バロネス》は②の効果により、魔法・罠・モンスター効果の発動を無効に破壊することができます。 この2つの効果を相手ターンに使うことで相手の動きを封じることでやり過ごし、次の自分のターンで相手を攻撃していくという流れに持っていくことを狙えます。
当然、相手の手札も相手ターンにドローするカード含めて6枚あるので、この2体の妨害効果をかわすこともできなくはないですが、6枚の手札すべてがこのターン中に使えてかつこの2体のモンスターを倒すことのできるカードとも限らないです。 先攻プレイヤーではほぼ自由に動けるのに対して、後攻側のプレイヤーはこの2回の妨害をどうかわすかを考えなければならないので、難易度はそれなりに高いです。
加えて、今回の展開で最初に使った莫邪をサーチする手段として《龍相剣現》や《白の聖女エクレシア》があります。 莫邪の効果で見せるための「相剣」カードまたは幻竜族モンスターも【相剣】デッキでは自然と多く採用することになるので、手札にこれらのカードがないということは少ないでしょう。 そのため、【相剣】デッキではこのような展開を安定的に行えるのが強みです。
先攻制圧で確実にゲームの流れをつかもう
新しいデッキを組むときはまず、先攻をとったときどのような妨害カードを盤面に揃えられるかを考えるといいでしょう。 そして、その盤面に到達するためにはどのカードが必要か、どういう展開をすれば盤面に揃えられるかを把握しておきましょう。 基本的にはサーチしやすいカード1枚から動けるのが理想的です。必要なカードが2枚以上になってしまうと1ターン目で手札にそろう確率は低くなってしまいます。
また、妨害カードをどのように使うかも非常に重要になります。【相剣】デッキの例では2妨害立てることができ、他のカードを組み合わせたり、さらに多くの妨害を立てるデッキもありますが、それでも相手の手札は6枚あります。 適切に妨害カードを使わないと気が付いたら逆転ということも少なくありません。 適切に妨害カードを使うためには、カードの知識や相手のプレイングを読む技術が必要になり非常に難しいです。たくさん対戦しながらどう妨害すればいいのかを考えていくといいでしょう。
手札誘発
現代遊戯王は圧倒的な先攻制圧により、後攻プレイヤーは苦しい戦いを強いられることが多いです。 これに抗う手段の一つが手札誘発カードです。相手ターンに手札から発動できるカードの総称で、手札から発動できるということは後攻プレイヤーが1ターン目から発動できる貴重なカードとなります。 これらのカードを利用することで後攻プレイヤーでも相手に対して妨害を行うことができ、先攻制圧盤面の構築をさせなくなるチャンスをつくりだすことができます。
代表的なカード
現代環境で多用される手札誘発カードを見て、どのように手札誘発が機能するかを見ていきます
《増殖するG》
手札から墓地に送ることで、相手が特殊召喚する度に1枚ドローできるというとても強力なカードです。これを使われてしまうと先攻プレイヤーは少ない特殊召喚で抑えていないと、後攻プレイヤーにとんでもない数の手札を与えてしまうことになります。 現代環境では多くのデッキが複数回の特殊召喚を経由することで制圧盤面をつくることになるので、場合によっては全く展開せずにターンを渡さざるを得ないこともあります。
そのあまりの強力さから海外の紙のカードのレギュレーションでは禁止カードに、日本のOCGのレギュレーションでは準制限カードに指定されています(2025年1月現在)。
《灰流うらら》
相手がデッキから手札にカードを加える効果やデッキから特殊召喚する効果をこのカードを手札から捨てることで止めることができます。 現代環境では展開を行うためのキーカードをデッキからサーチするという動きは非常に多くあるので使う場面は非常に多く遭遇します。 また、先述の増殖するGもドローする効果を持つものなので、このカードで効果を無効化することができます。そのため、先攻プレイヤー側としても持っておくと便利なカードです。 そのためこちらも採用率が非常に高いカードとして知られています。
《無限泡影》・《エフェクト・ヴェーラー》
《無限泡影》は罠カードでありながら自分フィールドにカードが存在しない場合、手札からも発動できる珍しいカードです。相手モンスターの効果を1ターン無効化することができます。 《エフェクト・ヴェーラー》も相手メインフェイズ限定で手札から発動できるモンスターカードで、相手のモンスター効果を1ターンだけ無効化することができます。 現代遊戯王ではモンスターカードの効果を起点に展開を行うことが多いので、この無効効果が有効に働く場面は多いです。
どちらも似たような効果を持ちますが、無限泡影は罠カードなので伏せてから使うことができたり、後攻1ターン目のフィールドががら空きの状態で使えたりするなどタイミングが広い点が嬉しいところです。 対してエフェクトヴェーラーは、フィールドが空でない場合も手札から発動できたり、チューナーモンスターなのでいざというときはシンクロ素材に活用できたりするなどの利点があります。 環境や自分のデッキの性質などを考えてどちらを採用するかを考えることになるでしょう
手札誘発がなぜ強いか
手札誘発カードの強みはその発動できるタイミングにあります。後攻プレイヤーとしてはこれが唯一の先攻プレイヤーにできる妨害の手段です。 例えば、先攻制圧の章で紹介した【相剣】デッキの展開例でいうと、莫邪を手札に加えるようなカードに対してうららを使えれば、相手の予定していた展開パターンに持っていけない可能性が生まれます。 莫邪の召喚時のトークンを特殊召喚する効果に対して無限泡影を使うことができれば、シンクロ召喚が行えずそのままターンを終了せざるを得ない場合もあり得ます。
また、多くの手札誘発カードは先攻プレイヤーにとっても使うことのできるカードです。 増殖するGを先攻プレイヤーが相手ターンに使えば、相手は反撃のためのモンスターを特殊召喚するたびドローを許すことになり、倒しきれなければ相手に大量のカードを使うチャンスを与えることになるだけではなく、ドローにより他の手札誘発カードをドローさせてしまい妨害される可能性が増えることになります。 他のカードも先攻展開プレイヤーの展開を止められるということは、同様に後攻プレイヤーの展開を止めることができるということです。 無限泡影は罠カードなので先攻プレイヤーは伏せれば使えます。他の手札誘発カードもほとんどはフィールドにカードがあっても発動できるので問題なく使用できるでしょう
他にも除去しにくい妨害として成り立つという点も優秀です。手札のカードを取り除くことができるカードは限られているため、例えば魔法・罠カードのように大嵐のようなカードであらかじめ破壊しておくということはやりにくいです。
手札誘発への対抗策
手札誘発カードは環境で多用されるため、その対策カードもよく使用されます。 《墓穴の指名者》は速攻魔法で相手の墓地のカードを取り除き、同名カードの効果を次のターンまで無効にします。手札誘発カードの多くはモンスターカードで墓地に送ってから発動することが多いため、先攻プレイヤーはこのカードを相手の手札誘発にチェーンして使うことで、相手の手札誘発カードの効果を無効化することができます。 《抹殺の指名者》は同様に速攻魔法でデッキから取り除いた同名カードの効果をターン終了時まで無効にできます。 こちらも先攻プレイヤーが相手の手札誘発カードの効果にチェーンして発動することで、相手の手札誘発カードの効果を無効にできます。同名カードをデッキに入れておく必要がありますが、墓穴の指名者と異なり罠カードも無効にできたりする点で優れています。 これらは強力な対抗策ですが、それぞれ準制限と制限カードなので確実に対策できるというものではないです。
他には効果の発動を無効にするカードを予め場に出してしまうというものもあります。 レベル3のモンスターを多用するデッキでは《No.75 惑乱のゴシップ・シャドー》を先に召喚することで、相手のモンスターの手札誘発カードを無効化することができます。 こちらをおとりにして本命の展開を通すといったことも可能です。
手札誘発はうまく使いこなそう
後攻プレイヤーの希望である手札誘発カードですが、後攻で勝てないから安易に手札誘発をたくさん入れよう、という考え方は危険です。 まず現代環境ではトッププレイヤーの集う世界大会ですら60%ほどは先攻プレイヤーが勝つゲームになっています。 まずは先攻できちんと勝てるようなプランをつくる、そのうえで余ったデッキ枠に手札誘発カードを入れることで後攻勝率も押し上げる、という考え方をするとよいでしょう。
手札誘発カードの強みはタイミングであり、効果そのものは相手のカード1枚を一時的に止めるカードがほとんどです。 例えばうららやヴェーラーで相手のモンスター効果を一時的に無効にできても、そのモンスターは場に居残り続けて最悪の場合は次のターンにまた効果を使われるということもあります。 手札誘発カードはあくまで一時しのぎで、次の自分のターンできちんと展開できなければその次のターンにまた相手にチャンスを与えてしまうことになります。
手札誘発を使うタイミングも重要です。【相剣】デッキの展開例では莫邪の効果を無効化すれば止まってくれそうですが、デッキの種類や相手の手札次第では最初に召喚されたモンスターではなく、そのモンスターによってサーチされるカードを無効にすることを狙うことがいい場合があったりと、判断は上級者でも非常に難しいです。 環境によって有効な手札誘発の種類が変わることもあります。環境によって手札誘発の使い方・入れる種類を柔軟に変えていくというのが大事です。
また、先攻をとった場合も相手が手札誘発を打ってきたことへの対抗策を考えておくことは大事です。常に対策するということはどうしても難しいですが、うまくカードが噛み合った場合限定で手札誘発の回避策を考えておけるとさらに勝率を伸ばすことができるでしょう。
捲り札・返し札
後攻で主に使う相手の盤面のカードを除去できるカード群を捲り札、もしくは返し札と呼びます。こちらも先攻盤面を崩す有効な手段となります。 主な捲り札の特徴の一つがその効果の強力さで、相手の複数枚のカードを除去できたり、相手の妨害や耐性を無視して除去できたりするものがあります。 《サンダー・ボルト》や《ハーピィの羽根帚》が該当します。 前者は相手フィールドのモンスターをすべて破壊し、後者は魔法・罠カードをすべて破壊します。昔に遊戯王やっていた人にはおなじみのカードで、かつては禁止カードになるほどのパワーカードでした。
しかし、現代のマスターデュエル環境ではこれらのカードは必須採用のカードというわけではありません。その理由や捲り札の考え方を説明していきます。
捲り札の弱点
捲り札の効果そのものは強力に見えますが、実は現代環境においてはいくつかリスクを抱えています。 1つ目は多くの捲り札が先攻では使い道がない点です。捲り札の多くは相手のフィールドのカードを除去するものですが、先攻においてはそもそも相手フィールドにカードはありません。 3ターン目以降に使えばいいのでは、と思うかもしれませんが、現代環境では1ターンのうちに強力なモンスターを並べることは珍しくなく、後攻1ターン目に勝負を決められることは珍しくありません。 このような高速化した現代環境で先攻において役に立たないカード1枚あるというのは無視できないリスクとなります。先攻では1枚でも多くの先攻制圧用のカードを揃えたいです。
もう1つはそもそも相手の盤面に対して捲り札が有効に作用しない場合があることです。 例えば《サンダー・ボルト》の場合、相手の盤面に《フルール・ド・バロネス》のような魔法カードを無効にできるカードがある場合、効果が通らないことになります。 効果を使わせることができると考えることもできますが、それなら他の展開用のカードでも同じ役割を果たせる可能性があります。
仮に効果が通ってもそれが有効に働かないというパターンというのもあります。 《超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ》のように効果による破壊への耐性を持つモンスターや、効果により墓地に送られてしまうことをトリガーに効果を発動してしまう【ティアラメンツ】デッキ(例えば《ティアラメンツ・カレイドハート》のようなカード)に対しては《サンダー・ボルト》は有効な捲り札にはなりません。 もちろん、捲り札といってもいろいろな種類があるため、これらのカードに有効な捲り札も存在します。しかし、環境でどのようなカードとよく出会うかを考えて適切な捲り札を選択するというのは結構難しいです。
また、手札誘発カードの方が有効に働くデッキというのも存在します。先攻制圧の例で出した【相剣】の展開パターンの場合、最後にバロネスが出てしまうので魔法・罠カードの捲り札1枚を使っても赤霄によるモンスター効果無効の妨害手段が残ってしまいます。また、攻撃力の高いモンスターが盤面に残っているのもそれなりに厄介です。 しかし、捲り札ではなく手札誘発カードの《無限泡影》ならば、展開途中の莫邪の効果を無効にしてしまうことで、そもそもシンクロ召喚のためのモンスターを揃えることができず、本来召喚されるはずだった妨害のためのモンスターを出させないでターンをもらうことができるかもしれません。 相手の手札次第では止めきれない場合がありますが、その場合は手札誘発なしだと相手の盤面にさらに妨害カードが並んでいる可能性が高く、やはり捲り札1枚では状況を逆転できないということになってしまうでしょう。
このように一見派手で強力な効果を持つ捲り札ですが、同時にリスクも抱えているため、現代環境では必ずしも必須のカードではないという状況になっています。 もちろん、捲り札の種類や自分の使っているデッキや環境で流行っているデッキの相性次第では、その強力な効果を存分に発揮できることもあるので適切に見極めれば心強いカードとなってくれるでしょう
具体的な例
現代環境でよく見かける捲り札をいくつか紹介して、その強い点と弱い点もそれぞれ見ていきたいと思います。
《サンダー・ボルト》・《ハーピィの羽根帚》のような全体破壊系魔法カード
先ほど紹介した2枚のカード以外にも《ライトニング・ストーム》など、相手のモンスターまたは魔法・罠カードをすべて破壊する魔法カードは捲り札として代表的です。 強みとしては、1枚のカードで複数枚のカードを一気に破壊することができるため、これ1枚で複数枚の妨害カードを除去できる可能性があることでしょう。 欠点としては、先ほどあげたように破壊に耐性を持つカードや破壊されることをトリガーに効果を発動するカードを使った妨害には利かないことが上げられるでしょう。特に破壊という除去手段は遊戯王において最もメジャーなので、それだけ破壊に対抗する手段をもつカードも多いです。
《拮抗勝負》
後攻でターンをもらい、そのままフィールドが空の状態でバトルフェイズに入り、即バトルフェイズ終了を宣言することでこのカードは手札からすぐに発動することができます。 自分のフィールドはこの発動した《拮抗勝負》が1枚のみなので、相手は自分のカード1枚のみしかフィールドに残せず、残りのカードを裏側で除外することになります。 裏側で除外したカードは基本的には基本的に再び手札に加えたりフィールドに戻すということはできないです。【ティアラメンツ】カードのように、効果の起点になることもないです。
弱点としては残す1枚のカードは相手が選べるため、強力なカード1枚を残すことができてしまう点です。《召命の神弓-アポロウーサ》のような1ターンに複数回効果を使えるカードが残ってしまうと、妨害数はそこまで減ってないということもありえます。 また、バトルフェイズを一度終了しないといけないというのは致命的な弱点です。これでは戦闘で相手のライフポイントを削ることはできないので、相手にターンを返してしまうことになります。 デッキタイプによっては後続となるカードを墓地や手札に残しつつ展開するものもあるので、このカードで盤面を処理できても結局次の相手のターンにやられてしまうということも普通にありえます。
《禁じられた一滴》
自分の手札・フィールドからカードを墓地に送り、その数だけ相手フィールドの効果モンスターの効果を無効にし、攻撃力も半減させられる効果を持つ速攻魔法です。 このカードの最大の強みは、相手はコストとして墓地に送ったカードと同じ種類のカードをチェーンできない点にあります。 つまり、モンスターカードをコストに発動すれば、バロネスのようなモンスター効果による魔法カードの発動無効を打てないことになります。 複数枚をコストにすればその数だけ無効にできるので、相手にチェーンされずに確実にモンスター効果を無効にできるのは魅力です。 また、速攻魔法なので先攻で引いてしまっても伏せておいて相手ターンに妨害として使うこともできます。
弱点はコストの要求が重い点でしょう。他の捲り札が1枚で複数枚をまとめて処理できたのに対して、こちらは複数枚を処理するために同じ数だけ追加で墓地に送らないといけません。 墓地に送ることで効果を使うカードが多いデッキや、フィールドに残りやすい永続系のカードが多く入るデッキでは比較的コストを用意しやすいでしょう。 自分で発動した魔法カードにチェーンする形でこのカードを打つと、発動した魔法カードもコストにできるので、こちらもコストを軽減するテクニックとして有用です。
【壊獣】モンスター
《海亀壊獣ガメシエル》など【懐獣】というカテゴリーに属するモンスターです。 相手フィールドのモンスターをリリースし、相手フィールド上に特殊召喚されるという特徴があります。 相手フィールドのモンスターをリリースするのはコストなため、相手が効果により阻止することはできません。リリースされることで効果を発動するようなモンスターはほぼいないので、効果の起点になることもないでしょう。
相手に攻撃力のそこそこ高いカードを渡してしまい、このカードで処理できるモンスターは1体までである点は弱いところではありますが、妨害効果や耐性効果を持つモンスターを確実に除去できるというのは他にない魅力でしょう。 似たようなカードとして《溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム》や《ラーの翼神竜-球体形》があります。これらのカードは複数枚をリリースすることができますが、使ってしまうと自分は通常召喚ができなくなってしまいます。 通常召喚をしなくても展開できるデッキならこちらを採用することも考えられるでしょう。
《三戦の才》
自分のターンのメインフェイズに相手がモンスター効果を使っているターンに使えるカードで、2枚ドロー・モンスターのコントロールを得る・手札を1枚デッキに戻すという強力な効果のうち1つを選ぶことができます。 状況に応じて強力な3種の効果を使い分けることができるカードで、モンスターの効果で妨害することが多い現代環境では使うタイミングは多くあります。 このカードのいいところは先攻でも使える点です。相手が手札誘発のモンスターカードの効果を使ってくれれば発動条件を満たすことができ、2枚ドローで展開用のカードを引きにいったり、相手の手札をデッキに戻すことで次の相手のターンの展開を制限することができます。
確かに使える場面は多いのですが、一度相手に効果を使わせないと発動できない点には注意です。上級者になるとこのカードの存在を警戒してメインフェイズ前に予め効果を使っておいたり、妨害となるカードとしてまず罠カードを使用することで、このカードの発動条件を満たさないようにするプレイをすることもあります。
まとめ
捲り札は強力な効果を持ちますが、同時に弱点も多くあります。そのため、現代環境では必ずしも採用するわけではないです。 それぞれのカードの特徴を見極めて、自分のデッキ・環境に合わせたカードの採用判断をするようにしましょう。
その他の戦術
先攻を取り盤面をつくり、次の自分のターンに相手に戦闘によりライフを奪うというのがほとんどのデッキにおいての基本的な戦術です。しかし、その他にもいくつかの戦術が存在します。 今の環境ではメジャーでないものもありますが、これらをいくつか紹介しておきます。
後攻特化型
ほとんどのデッキが先攻を取ることを逆手に取り、後攻に特化したデッキです。 後攻に特化する利点はいくつかあります。
まず、先攻後攻を決めるコイントスに影響を受けにくい点です。 相手も後攻特化デッキでない限り相手は基本的に先攻をとってくれるので、コイントスの結果に関わらず後攻になります。 後攻を自ら選択するため、捲り札の弱点の一つである先攻での使い道がないという問題も気にすることなく、捲り札を多くデッキに採用することができるのも特徴です。 また、バトルフェイズは後攻プレイヤーなら1ターン目から行えるため、バトルフェイズ中に使える効果も使いやすいです。 後攻プレイヤーは1ターン目からドローできるため、手札の数も一枚多いのも地味ながら大きな利点です。
これら後攻特化はいい事ずくめのように思えますが、それでも相手の先攻制圧盤面を崩すのが難しいというのが現代遊戯王の特徴でもあります。 【天盃龍】というテーマは後攻特化型のデッキとして環境トップクラスの実績を残しましたが、他のテーマでこれ以上に環境に活躍したテーマは存在しなかったことからもその難しさがわかると思います。
メタビート
現代環境で活躍するデッキに対抗するため、特殊召喚を互いに大幅に制限したり、環境主流となるデッキを永続系のカードで封殺しつつ、自分はその影響を受けないカードを使っていくことで戦う戦術です。
有名なカードとしては互いに特殊召喚ができなくなる《フォッシル・ダイナ パキケファロ》のようなモンスターや、同じ種族のモンスターを1体までしか存在させなくする永続罠カードの《センサー万別》があります。 これらに加えて大量の《神の宣告》のようなカウンター罠カードを採用し、これらのカードを突破するのを制限するなどして、相手の動きを徹底的に封じるなどの戦術が取られます。
決まれば徹底的に相手の動きを封じることができる一方で、後攻になってしまうとこれらのカードを用意する前に相手の展開が完了していて、こちらのメタカードが機能しにくいため勝率が落ちる傾向にあります。 また、それぞれのカードはサーチしにくく、手札の引きに依存しやすいという点も難点です。特に強力なメタカードはマスターデュエルでは制限がかかりやすい傾向にある点もこの戦術の向かい風となっています。 しかしながら、採用するカードをきちんと選べば、どんなに強力な環境デッキでも一方的に封じる可能性を秘めている恐ろしい戦術です。
先攻1ターンキル(FTK)
先攻で効果ダメージを利用するなどして1ターン目で勝利を狙う戦術です。First Turn Killを略してFTKとも呼ばれます。 FTKを安定して決めることは基本的には難しいです(そのようなことを実現できるカードは制限改定などで規制されやすいです)。現代環境だと必要なカードが手札に揃っても相手の手札誘発カードにより止められるリスクもあります。 そのため、現代環境ではFTKを狙うプランと同時にFTKが決まらなかった場合は普通の先攻制圧を行うプランを持つデッキが多いです。
【ギミックパペット】や【ライトロード】などがFTKを狙えるデッキとして有名です。
デッキ破壊
遊戯王において、デッキからカードをドローするときにデッキからカードが0枚だったプレイヤーは負けとなります。 このルールを使うことで、ライフポイントを削るのではなく相手の行動を遅延させつつ、デッキのカードを破壊していくことで勝利を狙う戦術が存在します。 高速化した現代環境で、少なくとも40枚あるデッキを削り切るのは難しいですが、特化したデッキならば今でも十分に可能性がある戦術です。
代表的なテーマとして【神碑】(ルーン)があります。《神碑の穂先》などの速攻魔法カードが主体で、共通効果としてEXデッキから「神碑」モンスターを特殊召喚するか、特定の効果を発動させつつ相手のデッキを除外するかどちらかを選択して使えるという効果を持っています。 フィールド魔法の《神碑の泉》は、「神碑」速攻魔法をデッキに戻しながらドローを行うことができ、次々に速攻魔法を使いながら相手を妨害しつつ相手のデッキの枚数を減らすことができます。 他のデッキ破壊カードは、デッキからカードを墓地に送るものがほとんどで、デッキからカードを墓地に送ることで相手のカードの墓地に送られたときの効果を起動してしまうというリスクがありますが、【神碑】はデッキのカードを除外できるため強力なデッキ破壊テーマとして知られています。
変わったところでは、手札誘発カードの《増殖するG》を使われたときに、あえて特殊召喚をたくさん行うことによりデッキを0枚にするという戦術も存在します。 こちらは相手依存になるためメインの勝ち筋になるわけではないですが、増殖するGを使われたときの対策として使われる場合があります。
バーン戦術
戦闘ではなく効果によるダメージを与えること(バーン)で勝利を狙うデッキです。 効果によるダメージは相手フィールドにモンスターがいる状態でもダメージを与えることができるため、相手の盤面のモンスターを無視してダメージを与えることができます。 また、バーン効果を防ぐカードが採用されていることも少ないので対策もやりにくいです。展開の際にライフコストを支払うタイプのデッキもあるため、そのようなデッキにとってバーン戦術は苦しい相手になるでしょう。
積まれているチェーンの数×400のダメージを与えられる《連鎖爆撃》を駆使したデッキは古くから有名なバーンデッキです。 【ヴォルカニック】デッキでは、《ヴォルカニック・エンペラー》のような強力なモンスターを駆使しつつバーン戦術を行うことができます。
注意するべき点は、バーン効果を与えることは必ずしも相手の展開を止めたり盤面のカードを減らしたりということにはつながらないという点です。 そのため、バーンデッキで相手を倒しきれなかった場合、相手の盤面にリソースが残ってしまうと逆にバーンデッキが押し切られることもあります。
参考資料
今回このドキュメントを作成にするために参考にした資料及び、最新の環境の情報などを発信しているこのドキュメントではカバーできていない情報を得られる場所や、個人的によく見る情報源をまとめておきます
Webサイト
遊戯王OCGカードデータベース
遊戯王OCGの公式なデータベースです。もっとも確実な情報を得ることができます。 カードのテキストや公式FAQを確認したい場合はこちらを見るとよいでしょう
遊戯王カードWiki
遊戯王OCGの非公式なデータベースです。単なるカードのテキストのみならず、カードの使い方やルールの詳細な解説なども掲載されています。 より深堀りしたい項目についてはこちらを見るのがオススメです。
YouTubeチャンネル
シーアーチャー
OCG・MDのプレイヤーで多くの実績を持つシーアーチャーさんが運営しているチャンネルです。 OCG・MDの最新情報について発信しており、特に最新の環境テーマの構築・展開例については非常に参考になると思います。
たすく
MDのデュエリストカップというイベントで何度も世界一位を獲得しているたすくさんが運営しているチャンネルです。 デュエリストカップ中も配信していることもあるので、そのプレイングや思考は間違いなく参考になるでしょう。
あまくだり
独特のコスプレ・声真似を交えて主に遊戯王関連の動画を投稿しているあまくだりさんのチャンネルです。 最新のMDの情報の紹介もしていますが、環境テーマではないファンデッキ寄りのテーマも紹介しているチャンネルです。 特に「クソカード診療所」と呼ばれる動画シリーズでは、環境では使うのがあまりにも難しいカードの使いみちを考察しており個人的におすすめです。